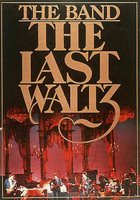Rubber Soul / The Beatles
ラバー・ソウル/ザ・ビートルズ
(1965年)
スタジオでの音楽的冒険を繰り広げた中期ビートルズの序章と呼ばれる作品。歌詞もサウンドも初期に比べ飛躍的な進歩を遂げている。60年代に起こった音楽的なムーブメントはほぼすべてビートルズが先導したと言って過言ではないが、この作品は「フォーク・ロック」の草分けにして代表作といわれている。
最後のロックンロール・ビートルズ
「ラバー・ソウル」とは、80年代のバンド・ブームの頃に大いに流行ったゴム底の靴のことでは当然なくて、文字どおり「ゴム製の魂」の意味である。なんでも、ソウル・シンガーがローリング・ストーンズの音楽を「プラスティック・ソウル」と言って馬鹿にしたところからこのタイトルを思いついたとか。発案のきっかけはともかく、とても文学的で洒落たタイトルだと思う。
ビートルズの音楽が変わりはじめたのは、このアルバムからと言われている。沈鬱な表情を浮かべたメンバーの写真(すこしタテに伸びている)をあしらったジャケットは、それまでの作品とは明らかに趣を異にしているし、詩もグッと深みを増した(これはボブ・ディランの影響だとか)。
「ノルウェイの森」にはシタールがダビングされているし、「イン・マイ・ライフ」ではテープの倍速回転が採り入れられている。ビートルズは続く「リボルバー」「サージェント・ペッパーズ」といったアルバムでサイケデリック=スタジオでの音楽の冒険を追求することになるが、この作品をその端緒とするのが通説だ。
とはいえ、私がこのアルバムを愛するのは、「ビートルズのスタジオ時代」がここからはじまったから、ではない。むしろ逆で、「ロックンロール・コンボとしてのビートルズ」がここで完成を見ているからである。
次作「リボルバー」の楽曲は、すでにライヴで再現不可能な域に達してしまっている。むろんそれも素晴らしいのだけれど、私はギリギリのところでライヴ・バンドとしての体面を保っている「ラバー・ソウル」のビートルズが、とても愛おしく感じられるのだ。
「ドライヴ・マイ・カー」「ユー・ウォント・シー・ミー」「君はいずこへ」「ウェイト」、そして「愛のことば」。これらの曲は実際にライヴで演奏されることはなかったけれど、彼らが殺人的なツアー・スケジュールをこなすことで培ったグルーヴが、たしかに息づいている。アルバム・タイトルどおり、ソウル・ミュージックの影響も大きいのだろう。
私事になってしまうが、私がビートルズをはじめてマトモに聴いたのはこのアルバムだった。たぶん、高校生の頃だろう。濃緑のアルバム・ジャケット、マッチョなグルーヴ、印象的なメロディ・ライン。いずれも文句なくカッコ良かった。ビートルズは断じて甘っちょろいポップスをやるバンドではなく、じつにイカしたロックンロール・バンドだったのだ。そのことが、痛いほどよくわかった。
たぶん、はじめて出会ったのが「サージェント・ペパーズ」や「ホワイト・アルバム」や「アビー・ロード」だったら、そんなふうには思えなかっただろう。今にして思えば、本当に幸福な出会いだった。
(誤解のないように付け加えておくが、断じて後期の諸作がつまらないと言っているのではない)