Last Waltz / The Band
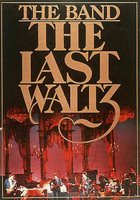 映画『ラスト・ワルツ』
映画『ラスト・ワルツ』
ザ・バンド
1976年、サンフランシスコで開催されたザ・バンドのラスト・ステージを記録した映画。ボブ・ディラン、エリック・クラプトン、ニール・ヤング、ジョニ・ミッチェル、ヴァン・モリソン、マディ・ウォータースなど、出演者も超豪華。監督は『タクシー・ドライバー』のマーティン・スコセッシ。
演出された「終わり」、それでも人生は続く
ザ・バンドの『ラスト・ワルツ』は、ロック映画の最高傑作のひとつである。
監督はマーティン・スコセッシ。『ラスト・ワルツ』が撮影されたのは1976年、ちょうど『タクシー・ドライバー』が公開された年だ。まさに絶頂期である。演出に緊張感がある。ロック映画にありがちな冗漫さがどこにもないし、ステージのライティングもカメラワークも、すべてが計算し尽くされている。そのくせ、ステージの躍動感・臨場感は失われていない。クライマックスでボブ・ディランが登場するシーンなど、ザ・バンドの面々の緊迫ぶり(リハなしのぶっつけ本番だったらしい)がリアルに伝わってきて、感動的である。
ヴァン・モリソンからマディ・ウォーターズまで、音楽の偉人たちが次々に登場するステージと、ザ・バンドのメンバーへのインタビューを中心としたドキュメンタリーが交互に語られる構成も、みごととしか言いようがない。この構成によって、『ラスト・ワルツ』は、ロック映画が通常持つことができない「物語」を持つことに成功している。
『ラスト・ワルツ』で語られる物語とは、ふたつの歴史物語である。ひとつは、「ザ・バンドの歴史」という物語。もうひとつは、「ロック・ミュージックの歴史」という物語。ふたつの物語は、それぞれが交錯し補完しあいながら、映画の最終幕で美しく「終わり」を迎える。『ラスト・ワルツ』は、ロック史上きわめて重要なグループの「終わり」に重ねて、「ロックの終わり」を描いた作品なのだ。
『ラスト・ワルツ』が開催された76年は、ロンドンとニューヨークでパンク・バンドが同時多発的に発生した年である。「ニューウェーヴの時代」はすぐそこまで来ていたのだ。セックス・ピストルズのジョニー・ロットンが「ロックは死んだ」とのたまうのは、この翌年のことである。
果たしてこの頃、本当にロックが「終わった」り「死んだ」りしたのかどうか。それはわからない。だが、「変質」していたのはたしかだった。
ロックは、70年代に入ってから急速に成長を遂げていた。なにしろ毎年、前年比25パーセント増しでレコードの売り上げが伸びていたのである。これにともない、スタジアム・コンサートも一般化し、『ラスト・ワルツ』が開催された76年には、ロックは完全に巨大産業になっていたのだ。表現も進化/深化を遂げ、ロックはかつてのような、いきがった若者のためのカウンター・カルチャーではなくなっていた。「死んだ」「終わった」は言い過ぎにしても、「変質」していたのは事実である。
おそらくはザ・バンドのロビー・ロバートソンも、その「変質」を敏感に感じ取っていたのだろう。彼は次のように語り、『ラスト・ワルツ』を企画する。
ロックとは旅すること。旅はもう、終わりだ――。
デビュー前のドサ回りで8年。デビュー後のスタジアムやホールを回るツアーで8年。計16年を「旅」に費やしてきた。この後も旅を続ける人生なんて、自分には耐えられない。『ラスト・ワルツ』でロバートソンは、幾度となくそう語っている。
ロック・ミュージシャンである以上、ツアーは避けられない。だが、彼はもともと、ステージがそんなに好きではなかったのだろう。ヒッチコック映画からタイトルをとった「Stage Flight/ステージ恐怖症」なんて曲もある(名曲です)。
人生を旅に費やすことをやめ、レコーディング・アーティストとして生きる。『ラスト・ワルツ』はもともと、彼が(主語は単数である)ステージ活動をやめるために企画した、壮大な「ステージ卒業式」だった。したがって、『ラスト・ワルツ』で終わるもの/終わらせるものとは、あくまで「ザ・バンドのコンサート活動」にすぎなかった。
にもかかわらず、ザ・バンドはほどなくして解散してしまう。レコーディング・アーティストになりたかったのは、じつはロバートソンだけだったのだ。他の連中はちがった。音楽以外にとりえもなけりゃできることもない、ホンモノの音楽バカだった彼らにとって、演奏することはそのまま、生きることだった。コンサート活動をやめてしまえば、演奏する場がなくなってしまう。
ザ・バンドにとどまっていても演奏ができないからこそ、各人はソロ活動に精を出しはじめた。ライヴをやらないザ・バンドは、ザ・バンドじゃなかったのである。
さらに、映画『ラスト・ワルツ』が78年に公開される。前述したように、「終わり」を美しく演出したこの作品は、ザ・バンドというグループが存続することを許さなかった。ファンでさえが、「ザ・バンドは終わった」と思いこんでしまったのである。
「『ラスト・ワルツ』はザ・バンドの解散コンサートである」という誤解が根強いのも、この映画があまりに美しく「終わり」を描いているためだ。
アメリカン・ミュージックの伝統を知り尽くした6人の達人ミュージシャンが織りなす音楽絵巻。それが、ザ・バンドの音だった。この6人でしか鳴らせない音、この6人でしか表現できない世界。ザ・バンドはまちがいなく、ワン&オンリーのグループだった。ことに、傑作といわれる初期の2枚――『ミュージック・フロム・ビッグ・ピンク』および『ザ・バンド』は、その傾向が強い。
だが、扇は要がなければ開かない。ザ・バンドの音楽は、ロビー・ロバートソンという要があったからこそ、花開くことができたのである。彼らが演奏する泥臭いルーツ・ロックが、単なる原点回帰で終わらなかったのは、ひとえにロビー・ロバートソンという優れたソングライター/コンセプト・メイカーを持っていたためだ。
「ルーツ・ミュージックにアメリカの歴史を歌い込む」というコンセプト、それをみごとに演出するリリシズム溢れる楽曲の数々。いずれも、ロバートソンの仕事である。ザ・バンドをザ・バンドたらしめていたもの、それはロビー・ロバートソンの知性と文学性だったのだ。
映画『ラスト・ワルツ』が傑作となったのも、煎じ詰めればロバートソンのコンセプトによるものだ。ロック・バンドがコンサート活動を休止する、ただそれだけのイベントが、いつしか大物ゲストを大勢呼んだスペシャル・コンサートとなる。映画化の話がトントンと決まる。売れっ子で多忙をきわめたマーティン・スコセッシが監督をかって出る。すべて、ロバートソンの「最後のワルツ」というコンセプトが魅力的だったからである。
そして、ロバートソンはバンドの歴史をしめくくる典雅なインスト曲「ラスト・ワルツのテーマ」を映画のために書き下ろす。この曲がなければ、映画がこれほどに美しく「終わり」を演出することはなかっただろう。
『ラスト・ワルツ』を企画したとき、ひょっとしたらロバートソンには、バンドの解散も、その後の身の振り方も、見えていたのではないかと思える。彼はザ・バンド解散後、ドリームワークス(現在はユニバーサルと合併)のレコード部門の重役として、ふかふかの椅子にふんぞり返る生活をすることになるのだ。
考えてみれば、ロビー・ロバートソンはものすごくビジネスマン向きの感性を持っている人である。頭は物凄く切れるし、アイデアも豊富だし、センスもいい。弁も立つ。機を見るに敏なところは『ラスト・ワルツ』で証明済み。その上、「アメリカン・ミュージックを知り尽くしたバンド」にいた過去もあるのだから、音楽業界でロバートソンに「ノー」と言うのはかなり難しいにちがいない。人に「ノー」と言わせないことが、ビジネスの成功条件である。
リタイヤしたロック・ミュージシャンの中で、第二の人生がもっとも成功しているのは誰か、といったらまちがいなくロビー・ロバートソンなのだ。
では、『ラスト・ワルツ』なんてちっとも望んでなかった残りの連中は? 天使のファルセット・ボーカリスト、リチャード・マニュエルはドラッグ中毒になったあげく、86年に自殺した。その他の連中はソロ活動したり、ザ・バンドを再結成したりしたが、残念ながら成功しているとは言いがたい。おそらくは今でも、小さなクラブでドサ回りをやってることだろう。
そういう事実を知った目で見ると、『ラスト・ワルツ』のロバートソンは、なんとも憎たらしいのである。ただ黙々と演奏しているだけのザ・バンドのメンバーの中で、この男だけが、キザったらしいギター・アクションをかまし、芝居がかった表情を幾度となく浮かべ、わざとらしく感動に打ち震えている。明らかに、カメラを意識しているのだ(それがまたカッコいいから癪に障る)。インタビュー・パートで「もうイヤだ」「もうたくさんだ」「もう終わりだ」を繰り返し、『ラスト・ワルツ』が必然だと強調しているのも、この男だけだ。
すべてを計算どおりに運び、現在もエグゼクティヴとして生活するロビー・ロバートソン。生涯一ミュージシャンから逸脱することができず、たった今もどこかでしょぼいステージをこなしているだろう残りの連中。明暗はハッキリ分かれた、ように見える。
やっぱり、正直な人間より利口な人間の方が成功するんだよね、この世の中。悪い奴ほどよく眠る、とは黒沢明もうまいことを言ったもんだ。
だが、最後にひとつだけ言いたい。
死んじまったリチャード・マニュエルやリック・ダンコはともかく、たとえばリヴォン・ヘルムとロビー・ロバートソン、ふたりを比べたとき、本当に幸福なのはどちらか決めることはできないはずだ。生涯ドサ回りの一ミュージシャンであるリヴォン・ヘルムの方が、レコード会社重役のロバートソンより、悠々と暮らしている、というようなことも、往々にして起こりえることである。音楽を裏切った人間は、音楽に愛されることもない。すくなくとも、リヴォン・ヘルムが今も毎日感じているはずの「演奏するよろこび」を、ロバートソンはもう、味わうことができないのだから。人生における幸福の総量は、地位や年収で計ることはできないのである。
ロビー・ロバートソンもたまに演奏してるって? 本気で楽しんでるはずないじゃないか。なにしろ、ステージ・フライトにおびえる線の細い男なんだから。
追記1:
映画『ラスト・ワルツ』は歴史に残る大傑作だが、映画公開と同時にリリースされたアルバムの方は、単なるサウンドトラックで大した作品ではない。オムニバス的な楽しみ方はできるけれど、ザ・バンドの演奏は粗いし、作品としてのトータルな魅力に欠ける。ザ・バンドのライヴを聴きたければ、ライヴ盤『ロック・オブ・エイジス』またはボブ・ディランとの競演盤『偉大なる復活』を聴くべし。いずれもロック史に残る大傑作ライヴである。
追記2:
映画『ラスト・ワルツ』の紹介としては、下記が詳しい。出演アーティストのプロフィールや代表アルバムにもふれていて、とても親切だ。
http://www.enjoy.ne.jp/~taira-a/TheLastWaltz.html
追記3:
DVD化に際して追加された特典映像「JAM #2」鑑賞記。じつはだいぶ前に書いたものだけれど、本稿に合わせて公開。
http://ameblo.jp/goatsheadsoup/entry-10012641497.html

